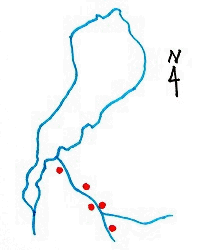 1.はじめに: 今から160年余り前の天保13年(1842年)10月 現在の野洲市 の三上地区で大事件が発生しました 近江天保一揆(天保十三年近江国三上藩一揆・水口藩一揆)です 野洲・栗田・甲賀三郡の農民約4万人が 幕府による検地(見分)の中止を 要求して決起し 三上村に押し寄せ 幕府が派遣した役人から10万日の日 延べを勝ち取ったのです 2.一揆の背景: 最初に 時代背景を概観してみます ・この時代 収税などの支配手段の基礎は検地と人別帳にありました
1.はじめに: 今から160年余り前の天保13年(1842年)10月 現在の野洲市 の三上地区で大事件が発生しました 近江天保一揆(天保十三年近江国三上藩一揆・水口藩一揆)です 野洲・栗田・甲賀三郡の農民約4万人が 幕府による検地(見分)の中止を 要求して決起し 三上村に押し寄せ 幕府が派遣した役人から10万日の日 延べを勝ち取ったのです 2.一揆の背景: 最初に 時代背景を概観してみます ・この時代 収税などの支配手段の基礎は検地と人別帳にありました検地は年貢米の算出基礎となる重要な 施策であり それゆえに過去に行われた 検地の結果を再吟味することは戒められ ていました ←検地の図 (「徳川幕府縣治要略」より) ・近江は 近江内外の多数の大小名、旗本、寺社領、直轄領などに分割され ていました(例えば 一村が多数の領主に服していた) 京の都に隣接した国としての特殊な存在でした ・天保の初期(天保3、5、7年)は 凶作による飢饉に苦しんでいました 各地で多数の一揆が発生しました 大塩平八郎の乱は天保8年です ・事件の前年(天保12年)は 水野忠邦の天保改革が宣言された年でした 3.驚くべき実地見分: 天保12年12月 村々の庄屋数百人を出頭させて京都奉行所が申し渡し たことは「新しく田を開発するため 諸川筋や湖べりの空き地を実地見分す る」とのことでした (検地と見分は異なりますが 以下本稿では単に検地と呼びます) しかし 翌年(天保13年)に始まった検地の実態は 人々を憤慨させるも のでした 例えば: ・彦根藩の領地は避け 主として相封(一村複数領主)地を調べた ・検地役人は公然と収賄し 贈賄した地区は素通りした ・土地の寸法を測定する竿の寸法を変更していた(本来の11尺6寸の竿に 12尺2分の目盛りをつけた→計測値は実際の面積より数%多くなる) 現在の近江八幡市から始まった検地の状況を見守っていた野洲川流域の人 々は その不条理なやり方の対抗策を練りました
野洲川上流の甲賀地区と野洲川下流の 野洲・栗田地区では それぞれ庄屋大会 が開かれました 天保13年9月26日に開かれた下流地 区の庄屋大会は 現在の守山市立田町に ある立光寺(りっこうじ)でした ←立光寺 立光寺の横(写真向かって左)には野洲川の堤防が高く立っていました 野洲川は南流と北流とに分岐していましたが 天井川であるため 台風によ る堤防決壊の被害を避けるため 南北流の中間を掘り下げて新しい川を引き ました 立光寺は古い南流の堤防横にあります
当時 堤防は竹で覆われていた かも知れません 現在 立光寺横 の堤防上からは 三上山(近江富 士)を眺めることができます 手前一面の草むらは 南流が埋め 立てられた跡です 三上山 ↓
4.農民の蜂起: 天保13年10月14日の夜 矢川神社(やがわじんじゃ:甲賀市甲南町) に数千人の農民が集結しました 水口藩の警備の武士はおとなしく見守って いたようです
矢川神社は JR草津線 甲南駅の北西1キロ位の 位置にあります
参道を進むと太鼓橋に出会います その奥には立派な楼門がありますが 現在は修復中のため 見られません ←矢川神社参道 ↓矢川神社前の太鼓橋

境内には 蕪村の詠んだ句碑があります 甲賀衆の しのびの賭や夜半の秋 ←本殿 ↓本殿を飾る彫刻
矢川神社の参道入口に近い矢川橋の傍に「天保義民メモリアルパーク」が あります
←天保義民メモリアルパーク ↓
5.三上村を目指して: 矢川神社に集結した農民達は北(北西)の三上村を目指して移動します 三上村には検地役人が本陣を構えていたからです 甲賀地区と野洲・栗田地区とは 事前の計画に基づいて緊密な連絡を取り合 っていました
現在の国道1号線が野洲川を 横切っているのは横田橋です この横田橋あたりから上流は横 田川と呼ばれていました 現在の横田橋から500メート ル位南(上流)に 横田の渡し の跡があります 江戸時代は橋がなく 流量の多い3〜9月には 船による渡しとなっていま した 明治時代(明治24年:1890年)には長大な板橋が架けられたそ うです 現在残っているのは明治時代に架けられた横田橋の石垣です
←横田橋(渡し)跡 (次に出てくる三雲の「天保義民之碑」 は 対岸の丘の上にあります) 常夜燈(文政5年=1822年建立) ↓
2万人余りに膨れ上がった群衆は このあたりで 渇水期の横田川を渡っ たのでしょう この川の向こうは三雲です 三雲村の庄屋は 沢山の握り飯 を作って疲れた群衆に振舞ったそうです 16日早朝に石部の宿に達しました そこには膳所藩の武士が警護にあた っていましたが 対応は穏やかでした ここでも炊き出しが供され 疲れと 空腹が癒されました
←天保義民之碑 (明治31年(1898年)建立) 義民碑の丘から見る三上山 ↓
6.一揆の終結: 16日の昼頃 甲賀地区と野洲・栗田地区とが合流した群衆は 検地役人 のいる三上村を包囲しました その数は4万人を超えたそうです 一揆の要求は 現に進行中の検地(見分)を即時中止してもらいたい とい うことでした 何回かのやりとりの後 16日夜に至り 幕府役人が証文を したためたことで群衆は解散しました 証文は 検地(見分)を10万日延期する(=中止) というものでした ここに至るまで 一人の死傷者もありませんでした しかし 事件後の幕府の仕打ちは凄惨でした 一揆に関わった要人に過酷な 拷問を加えた上 江戸送りにしました 三上村の庄屋 土川平兵衛(つちか わへいべい)他の主要人物は全員が抹殺されました
←野洲川と三上山 (「近江名所図会」より) 当時の三上山周辺の風景はこのようだっ たのでしょう 山裾中央の森は御上神社 (みかみじんじゃ)だと思われます 野洲川のこの辺りは 古くは 妓王井川 の故事の舞台となりました 写真でみる三上山 ↓

国道8号線を野洲川方面から来られる 場合 野洲川を超えて2つ目の信号を右 折すると「天保義民碑 是より一丁」の 道標がありますので 左に折れます ここは三上山登山口で 車1台がやっと 通れる道です 山道をちょっと登りかけ ると義民碑前の広場に着きます 検地役人が本陣を構えた大谷家は この道の近くです
←天保義民碑の道標 義民碑前の広場 ↓

←天保義民碑 一揆から約50年後の明治28年(1895年) 「天保義民碑」 がここに建立されました 義民碑の拓本(部分) ↓
土川平兵衛辞世の歌 ↓
人のため身は罪とがに近江路と 別れて急ぐ死出の旅立ち
←御上神社付近から見た三上山 義民碑は写真左手奥の麓にあります 手前の田は昭和の悠紀斎田です 毎年ここで 「お田植祭り」が行われます 余談をひとつ: 明治24年(1891年)5月11日に いわゆる大津事件が起こりました 日本を訪問中のロシア皇太子ニコライが 大津市で警備の巡査・津田三蔵に 切りつけられました 津田巡査は三上村の交番に勤務していました その交 番は 上の写真の(写っていませんが)前方右にあったそうです
大津の代官所で責め殺された 人々は近くの観念寺の墓に葬ら れました 観念寺は 大津赤十字病院の近 くにあります ←観念寺に残る過去帳(左) 江戸送りの途中に絶命した人は馬捨て場に捨てられ 江戸の奉行所で獄死 した土川平兵衛他の犠牲者は 小塚原に捨てられたそうです 7.おわりに: 三上村の庄屋だった 土川平兵衛さん他 一揆の中心人物は義民として顕 彰されています 庄屋は 体制側としても身をおくことができる立場にも拘 わらず 被体制側の農民の立場に立ち 義のために殉死した故でしょう 「第9回全国義民サミット」が 今年(2005年)11月19−20日に 野洲市文化ホール(JR野洲駅から徒歩2分)で開かれます 参加費無料 ・19日(土)13:00−17:00 基調講演:「近江義民の特色と天保一揆」国士舘大学教授 保坂 智氏 シンポジウム:「次世代に「義」の心をどう伝えるか」 ・20日(日)9:00〜 義民関係史蹟めぐり(県外参加者) 野洲市銅鐸博物館では 「近江天保一揆とその時代」展が 11月20日 まで開催されています この稿は 野洲市三上のコミュニティセンター(公民館)で開かれている 「楽しい歴史教室」での学習に基づいて書きました 近江天保一揆に関する著作は沢山ありますが この稿は主として 「天保の義民」松好 貞夫著 岩波新書 1962年12月20日発行 を参照しました この新書は一時絶版になりましたが 滋賀県出身の女性実業家の熱意で復刊 された ということです 掲載済みの関連記事:(本稿に関連する次の記事もご笑読ください) 1)野洲川 ⇒ 「消え行く天井川」 2)妓王井川 ⇒ 「妓王井川」 3)三上山 ⇒ 「三上山縁起」 4)悠紀斎田 ⇒ 「お田植祭り」 5)銅鐸博物館 ⇒ 「山乃神」 (散策:2005年10月20日) (脱稿:2005年11月7日) ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ